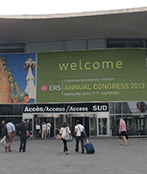
9月9日ERS(European Respiratory Society:欧州呼吸器学会)Annual Congressにて、3万件以上のサンプルを集めた2つのコホート試験の結果が発表された。
喘息はcommon diseaseであるにもかかわらず、さまざまなタイプがあることはあまり知られていない。その中で、なぜ特定の患者がより重症な病状を呈するのかは専門医もわかっていない。こうした背景のもと、The EU-funded U-BIOPRED*プロジェクトは、より個別化した治療を開発することを目的に、それぞれの重症喘息患者がどのように異なるのか、将来的に疾患をサブグル-プに分けられるかについて研究している。
一つ目の試験の結果、成人および小児の重症喘息には、それぞれ共通の特徴があることがわかった。この試験から得られた主な知見は下記である。
<成人>
・55%の重症喘息患者は定期的に経口ステロイドを服用しているにもかかわらず、軽症~中等症喘息患者に比べ、重度の気道閉塞を有している。
・重症喘息患者は、高用量のステロイドを使用しているにもかかわらず、今なお増悪などの重度の症状を経験している。
<小児>
・気道閉塞のレベルは、重症であっても軽症~中等症と同程度である。
・重症グループでは、呼気中一酸化窒素濃度(FeNO)レベルが高い。
当試験の筆頭著者であるDavid Gibeon氏は、「この初めての知見が、喘息患者に存在するサブグループの概要を示した。われわれが並行して行っている試験では、なぜより重症になるとより治療に反応しなくなるのかを、多くの異なる分子レベルで調べている。個々の喘息患者の治療と、より個別化したアプローチの開発に役立つであろう」と述べた。
二つ目のU-BIOPRED試験では、エレクトロニックノーズを用いて喘息患者の呼気サンプルを分析している。この調査の目的は従来の臨床的特徴ではなく、呼気の分子パターンで患者を分類することである。この試験では57例の患者の呼気サンプルから、重症患者の4つのサブグループの共通パターンを見つけることができた。
U-BIOPREDプロジェクトのリーダーPeter Sterk氏は、「この両方の試験から得られる知見は、われわれを重症喘息のより深い理解に一つ近づけた。このような条件の患者は増悪と症状を繰り返し、治療にもよく反応しないが、なぜこのようになるのかはわからない。このような方々の生活を改善するために、CTから喀痰、患者の遺伝子解析、気管支鏡の結果まで幅広いサンプルから、膨大な分析を開始して各々の患者の生物学的かつ臨床的な“指紋”を作る必要がある。U-BIOPREDプロジェクトは、このような患者の個別化医療の開発にわれわれを近づけるであろう」と述べている。
*U-BIOPRED(Unbiased Biomarkers for the Prediction of Respiratory Disease):ヨーロッパにおける教育機関、製薬企業、患者団体の共同組織
(ケアネット 細田雅之)