大学での人事評価、教授への昇進で重視されるのは?/BMJ

大学における研究者の評価は従来型の基準を重視していることが、世界各国より抽出された大学の横断研究の結果、明らかになった。カナダ・マギル大学のDanielle B. Rice氏らが報告した。教授の評価や在職期間の付与に用いる基準については変更することが推奨されているが、世界で適用されている昇進や在職期間の基準について、これまで系統的な評価は行われていなかった。結果を踏まえて著者は「大学は、非従来型の基準を奨励することを考慮すべきである」とまとめている。BMJ誌2020年6月25日号掲載の報告。
論文数などの従来型基準と、被引用数等の非従来型基準について調査
研究グループは、世界大学ランキングのライデン・ランキングから無作為に選んだ170大学を対象に、助教(assistant professor)、准教授(associate professor)および教授(professor)の評価と終身在職権付与に用いるガイドラインについて調査した。従来型基準5項目(査読論文数、論文における著者名の記載順位、論文掲載誌のインパクトファクター、助成金獲得、国内外での研究の認知)、および非従来型基準7項目(論文被引用数、データ共有、オープンアクセスの論文掲載、研究登録、論文発表ガイドラインの順守、研究の影響に関するオルトメトリクス、研究休暇制度)についてガイドラインへの記述状況などを調べた。
従来型基準の中でも論文数を重視する大学がほとんど
170大学中、生命医科系学部のある大学は146校で、92校に適格なガイドラインが存在した。ガイドラインに従来型基準5項目が記載されていた割合は、査読論文数95%(87校)、論文における著者名の記載順位37%(34校)、論文掲載誌のインパクトファクター28%(26校)、助成金獲得67%(62校)、国内外での研究の認知48%(44校)であった。
一方、非従来型基準については、論文被引用数(26%、24校)および休暇制度(37%、34校)については記載されている大学が多かったが、研究の影響に関するオルトメトリクス(3%、3校)とデータ共有(1%、1校)についてはまれで、他の3項目(オープンアクセスの論文掲載、研究登録、論文発表ガイドラインの順守)のガイドラインへの記載は確認できなかった。
教授への昇進評価に関するガイドラインでは、従来型基準が非従来型基準より多かった(従来型基準54.2% vs.非従来型基準9.5%、平均群間差:44.8%、95%信頼区間[CI]:39.6%~50.0%、p=0.001)。ガイドラインが利用可能かどうかについては、地域によるばらつきが観察された(オーストラリア100%[6/6校]、北米97%[28/29校]、欧州50%[27/54校]、アジア58%[29/50校]、南米17%[1/6校])。
(医学ライター 吉尾 幸恵)
原著論文はこちら
Rice DB, et al. BMJ. 2020;369:m2081.
[ 最新ニュース ]

lepodisiran、400mg投与で半年後のLp(a)値を93.9%低下/NEJM(2025/04/17)

TAVI生体弁比較、SAPIEN 3 vs.Myval/Lancet(2025/04/17)

抗血小板薬併用療法のde-escalationの意味わかる?(解説:後藤信哉氏)(2025/04/17)

慢性期心不全患者への水分制限は不要!?(FRESH-UP)/ACC(2025/04/17)

セフトリアキソンで腎盂腎炎を伴う腸内細菌目細菌菌血症を治療できるか(2025/04/17)

日本の男性乳がんの生存率、女性乳がんと比較~12府県のがん登録データ(2025/04/17)

若年性認知症患者、過去30年間で2倍超(2025/04/17)

医師からのメッセージ、AIが作成しても患者の満足度は高い(2025/04/17)
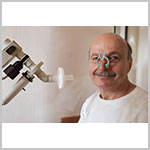
喘息の検査には時間帯や季節が影響する(2025/04/17)

専門家はこう見る
大学の昇進人事で出産や病気による休業期間の考慮には驚いた(解説:折笠秀樹氏)-1258
コメンテーター : 折笠 秀樹( おりがさ ひでき ) 氏
統計数理研究所 大学統計教員育成センター 特任教授
滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 特任教授
J-CLEAR評議員