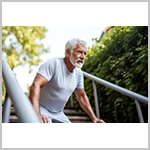
運動や日常生活の中で骨にわずかな衝撃を与えるだけで、加齢に伴う骨密度(BMD)の低下を抑制できる可能性のあることが、ユヴァスキュラ大学(フィンランド)のTuuli Suominen氏らによる研究で示唆された。大腿骨頸部と呼ばれる股関節の重要部位に焦点を当てて運動による介入の効果を検討したこの研究の詳細は、「Bone」1月号に掲載された。
加齢に伴い運動量は減り、それとともに骨密度や骨の健全性(integrity)は低下する。加齢に伴う骨の強度の低下はある程度は避けられない現象だが、高齢になっても運動を行うことで骨の強度を維持し、その低下速度を遅らせることができる可能性はある。それを確かめるため、Suominen氏らは、座位行動の多い70歳以上の男女299人(平均年齢74±4歳、女性58%)を対象に1年間にわたる運動介入の効果を検討した研究(PASSWORD試験)のデータを用いて、運動と骨の強度との関連を検討した。
対象者は、筋力、持久力、バランス、柔軟性の改善に焦点を当てた1年間の運動プログラムに取り組んでいた。試験開始時と介入から6カ月後に、対象者が平均6.6日、1日14時間にわたって装着した活動量計での測定結果を基に、1日当たりの骨形成指数平均スコア(骨の形成につながる活動を指数化したもの)、受けた衝撃(低・中・高強度)の回数や活動の強度(座位、軽度・中強度〜強度の身体活動)を評価した。また、試験開始時と12カ月後に、DXA法(二重X線吸収法)で大腿骨頸部のBMDを測定し、大腿骨近位部の構造力学的解析により骨の断面積(CSA)と断面係数を算出した。論文の共著者である同大学のTiina Savikangas氏は、「短時間の身体活動でも骨格には大きな影響を与える可能性があるため、われわれは個々の衝撃の回数と強度の観点からも運動について調べた」と同大学のニュースリリースで説明している。
試験参加者は介入開始から6カ月時点で、測定したあらゆる活動量が増えた一方で、座位時間は減っていた。また、介入終了時には、BMDは0.4%低下していたが、CSAは維持され、断面係数はわずかに増加していた。介入開始から6カ月時点で計測した身体活動の指標のうち、骨形成指数、高強度の衝撃、中強度〜高強度の身体活動と、12カ月間でのBMDの変化との間には正の相関が認められ、身体活動の強度が高いほど、BMDの低下は抑制されることが示唆された。
こうした結果を受けてSuominen氏は、「骨密度の低下を抑える上で鍵となるのは身体活動の強度と衝撃の強さだ。例えば、ランニングや早歩きをした人での方が、普通のペースで歩いた人よりも効果がはるかに高かった」と話す。同氏は、「高強度の身体活動は、早歩きや階段の昇降などの形で日常生活の中に少しずつ取り入れることが可能だ。ジャンプのような衝撃を加えるには、実際にジャンプしなくても、まずつま先立ちになり、それからかかとを落とせばよい」と話す。そして、「70代や80代であっても、このような運動を日課に加えることは容易だ」と付け加えている。
[2024年1月17日/HealthDayNews]Copyright (c) 2024 HealthDay. All rights reserved.利用規定はこちら