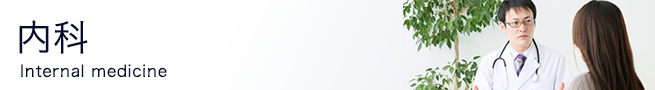日本のプライマリケア医における認知症診断の開示に関する調査

日本の認知症患者は、2025年には700万人に達すると予測されている。現代の倫理学者たちの結論では、認知症診断を完全に開示することが患者にとって最善の利益につながるとされているが、この関連性は、日本ではまだ研究されていない分野である。浜松医科大学のMichiko Abe氏らは、認知症診断の開示の実践に対するプライマリケア医の見解について調査を行った。BMC Family Practice誌2019年5月23日号の報告。 このqualitatively driven mixed methods projectでは、農村部と都市部別のサンプルを用いて、プライマリケア医24人を対象に、半構造化面接を行った。すべてのインタビューは、言葉どおりに記録し、テーマ別に分析を行った。研究チームは、テーマが飽和に達するまで、コンセプトを繰り返し議論した。サマリーは参加者に配布し、フィードバックを最終分析に組み込んだ。