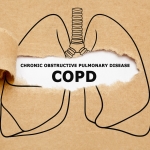
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療において、吸入ステロイド薬(ICS)・長時間作用性β2刺激薬(LABA)・長時間作用性抗コリン薬(LAMA)の3剤を1つの吸入器で吸入可能なトリプル製剤が使用可能となっているが、トリプル療法を用いてもCOPD増悪や入院に至る患者が存在する。COPD増悪はQOLを低下させるだけでなく、呼吸機能の低下や死亡リスクの上昇とも関連することが知られており、新たな治療法が求められている。
そこで、さまざまな分子に対する分子標的薬の開発が進められている。その候補分子の1つにTSLPがある。TSLPは、感染や汚染物質・アレルギー物質への曝露などにより気道上皮細胞から分泌され、炎症を惹起する。TSLPはタイプ2炎症と非タイプ2炎症の双方に関与しているとされており、TSLPの阻害はCOPDの幅広い病態に対してベネフィットをもたらす可能性がある。そのような背景から、すでに重症喘息に用いられているヒト抗TSLPモノクローナル抗体テゼペルマブのCOPDに対する有用性が検討されている。米国胸部学会国際会議(ATS2024 International Conference)において、英国・マンチェスター大学のDave Singh氏が海外第IIa相試験「COURSE試験」の結果を発表した。
試験デザイン:海外第IIa相無作為化比較試験
対象:トリプル療法を用いているにもかかわらず、過去12ヵ月以内に中等度または重度のCOPD増悪が2回以上発現した40~80歳のCOPD患者333例(喘息患者および喘息の既往歴のある患者は除外)
試験群(テゼペルマブ群):テゼペルマブ(420mg、4週ごと皮下注射)+トリプル療法を52週間(165例)
対照群(プラセボ群):プラセボ+トリプル療法を52週間(168例)
評価項目:
[主要評価項目]中等度または重度のCOPD増悪の年間発現回数
[副次評価項目]気管支拡張薬吸入前の1秒量(FEV1)、QOL、安全性など
主な結果は以下のとおり。
・対象患者のうち、過去12ヵ月以内に中等度または重度のCOPD増悪が3回以上発現した患者が41.1%(137例)を占め、血中好酸球数300cells/μL以上の患者は16.8%(56例)にとどまっていた。
・主要評価項目の中等度または重度のCOPD増悪の年間発現回数は、テゼペルマブ群がプラセボ群と比較して数値的に17%低下したが、統計学的有意差は認められなかった(90%信頼区間[CI]:-6~36、片側p=0.1042)。
・サブグループ解析において、血中好酸球数が多い集団でテゼペルマブ群の中等度または重度のCOPD増悪の年間発現回数が少ない傾向にあった。血中好酸球数(cells/μL)別のレート比および95%CIは以下のとおり。
150未満:1.19、0.75~1.90
150以上:0.63、0.43~0.93(post hoc解析)
150以上300未満:0.66、0.42~1.04
300以上:0.54、0.25~1.15
・52週時における気管支拡張薬吸入前のFEV1のベースラインからの変化量(最小二乗平均値)は、テゼペルマブ群26mL、プラセボ群-29mLであり、テゼペルマブ群が改善する傾向にあった(群間差:55mL、95%CI:14~96)。
・52週時におけるSt. George’s Respiratory Questionnaire(SGRQ)スコアのベースラインからの変化量(最小二乗平均値)は、テゼペルマブ群-4.80、プラセボ群-1.86であり、テゼペルマブ群が改善する傾向にあった(群間差:-2.93、95%CI:-6.23~0.36)。
・52週時におけるCOPDアセスメントテスト(CAT)スコアのベースラインからの変化量(最小二乗平均値)は、テゼペルマブ群-3.04、プラセボ群-1.18であり、テゼペルマブ群が改善する傾向にあった(群間差:-1.86、95%CI:-3.31~-0.40)。
・有害事象はテゼペルマブ群80.6%、プラセボ群75.0%に発現したが、新たな安全性シグナルはみられなかった。
Singh氏は、全体集団では主要評価項目を達成できなかったものの、血中好酸球数が多い集団でテゼペルマブの有効性が高かったことを指摘し、血中好酸球数150cells/μL以上の集団がテゼペルマブによるベネフィットを得られる集団となる可能性があると考察した。
(ケアネット 佐藤 亮)