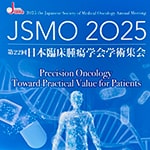
belzutifanはHIF-2α阻害薬として米国で初めて承認された薬剤であり、日本でも承認申請中である。独自の作用機序を有し、貧血および低酸素症を含む特有の有害事象(AE)プロファイルを示すことが明らかになっている。腎細胞がん患者を対象にbelzutifanの安全性プロファイルを評価することを目的として、4つの臨床試験の事後統合解析が実施され、米国・テキサス大学MDアンダーソンがんセンターのEric Jonasch氏が結果を第22回日本臨床腫瘍学会学術集会(JSMO2025)で発表した。
本解析は、既治療の進行淡明細胞型腎細胞がん(RCC)患者を対象とした第I相LITESPARK-001試験、第II相LITESPARK-013試験、第III相LITESPARK-005試験、およびフォン・ヒッペル・リンドウ(VHL)病関連腫瘍患者を対象とした第II相LITESPARK-004試験から、belzutifan 120mgの1日1回経口投与を受けたRCC患者を対象に実施された。
主な結果は以下のとおり。
・対象となった患者は計576例で、各試験の内訳はLITESPARK-001が58例、LITESPARK-013が76例、LITESPARK-005が381例、LITESPARK-004が61例であった。
・ベースラインの患者特性は年齢中央値が61歳(範囲:19~90)、男性が76.7%、ECOG PS 0~1が98.3%を占めた。西欧39.2%/北米38.4%/日本を含むその他の地域からの参加 が22.4%であった。
・全体として、572例(99.3%)に何らかのAEが認められ、355例(61.6%)にGrade3以上のAEが発現した。
・288例(50.0%)でAEによる用量調整が必要となったが、AEによる治療中止は37例(6.4%)にとどまった。
・最も多く認められたAEは貧血(ヘモグロビン低下を含む、84.2%)で、疲労(42.7%)、悪心(24.1%)、呼吸困難(21.4%)が続いた。
・多く認められたGrade3以上のAEは貧血(28.8%)、低酸素症(12.2%)であった。
・主なAEの初回発現時期中央値(範囲)は、貧血が29日(1~834)、低酸素症が31日(1~952)、疲労が42日(1~1,017)、悪心が43日(1~1,346)、呼吸困難が57日(1~911)であった。
・貧血を認めた485例のうち、111例(22.9%)は赤血球造血刺激因子製剤(ESA)のみ、85例(17.5%)は輸血のみ、62例(12.8%)はESAと輸血で治療された。患者当たりのESA投与回数の中央値は5回、輸血回数の中央値は2回であった。回復までの期間中央値は70日であった。
・低酸素症を認めた94例のうち、66例(70.2%)が酸素療法を受けていた。酸素吸入の期間中央値は9日、回復までの期間中央値は11日であった。
・治療関連有害事象(TRAE)は526例(91.3%)に認められ、Grade3以上は217例(37.7%)で発現した。Grade5のTRAEとして、多臓器不全が1例報告されている。
Jonasch氏は今回の結果について、有害事象は比較的早期に発現し、初回発現時期の中央値は治療開始から3ヵ月以内であったとし、想定されたとおり貧血と低酸素症が多くみられ、用量調整およびESA/輸血(貧血)・酸素療法(低酸素症)により管理されたとまとめている。
(ケアネット 遊佐 なつみ)