尿崩症診断、コペプチン測定が従来法を上回る精度/NEJM

尿崩症の診断について、間接水制限試験と比べて高張食塩水負荷試験による血漿コペプチン値測定のほうが診断精度は高いことが、ドイツ・ライプチヒ大学のWiebke Fenske氏らによる検討の結果、示された。間接水制限試験は、現行参照すべき基準とされているが、技術的に扱いが難しく、結果が不正確である頻度が高い。研究グループは、尿崩症にアルギニンバソプレシンが関与していることから、アルギニンバソプレシン前駆体由来の代替マーカーである血漿コペプチンを測定する方法の有用性を検討するため、間接水制限試験と比較した。NEJM誌2018年8月2日号掲載の報告。
水制限試験vs.高張食塩水負荷試験の診断精度を検証
試験は2013~17年に、スイス、ドイツ、ブラジルの11施設で、低張多尿であった16歳以上の患者156例を集めて行われた。被験者には水制限試験と高張食塩水負荷試験の両方を受けてもらい3ヵ月間のフォローアップ受診を行った。高張食塩水負荷試験では、高張食塩水を静注後、血漿ナトリウム値が150mmol/L以上となった時点で血漿コペプチン値を測定した。主要アウトカムは、最終参照診断と比較した各試験の全体的な診断精度であった。参照診断は、コペプチン値をマスキングし、病歴、試験結果、治療効果に基づき確定した。
コペプチンカットオフ値>4.9pmol/Lの診断精度96.5%
両試験が行われたのは144例で、最終診断は、原発性多飲症82例(57%)、中枢性尿崩症59例(41%)、腎性尿崩症3例(2%)であった。解析には141例(女性66%)が包含された。そのうち、間接水制限試験で正しく診断が下されたのは108例(診断精度76.6%、95%信頼区間[CI]:68.9~83.2)であったのに対し、高張食塩水負荷試験(コペプチンカットオフ値>4.9pmol/L)では136例(96.5%、92.1~98.6)で正しい診断が下された(p<0.001)。
また、間接水制限試験で、原発性多飲症と部分型中枢性尿崩症を正しく鑑別できたのは77/105例(73.3%、63.9~81.2)であったが、高張食塩水負荷試験では99/104例(95.2%、89.4~98.1)であった(補正後p<0.001)。
重篤な有害事象は、間接水制限試験で入院に至ったデスモプレシン誘発性低ナトリウム血症1例が報告された。
(ケアネット)
[ 最新ニュース ]

FDAへの医療機器メーカーの有害事象報告、3分の1が遅延/BMJ(2025/04/04)

フィネレノン、2型DMを有するHFmrEF/HFpEFにも有効(FINEARTS-HFサブ解析)/日本循環器学会(2025/04/04)

急性GVHDとICANSに対する新たな診断法の開発/日本造血・免疫細胞療法学会(2025/04/04)

市中肺炎へのセフトリアキソン、1g1日2回vs.2g1日1回~日本の前向きコホート(2025/04/04)

抗精神病薬の血中濃度、年齢や性別の影響が最も大きい薬剤は(2025/04/04)
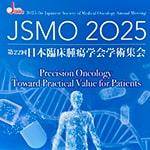
遺伝性消化管腫瘍診療に対する多施設ネットワークの試み/日本臨床腫瘍学会(2025/04/04)

幹細胞治療が角膜の不可逆的な損傷を修復(2025/04/04)

普通車と軽自動車、どちらが安全?(2025/04/04)

専門家はこう見る
尿崩症の診断におけるコペプチンの測定(解説:吉岡成人氏)-906
コメンテーター : 吉岡 成人( よしおか なりひと ) 氏
NTT東日本札幌病院 院長
J-CLEAR評議員