宿日直や自己研鑽はどう扱う?~医師の働き方改革

厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会(第9回)」が9月3日開かれ、今年度末のとりまとめに向け具体的な議論が開始された。医師の時間外労働の上限時間数の設定をはじめとした対応を議論していくにあたり、座長を務める岩村 正彦氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、(1)働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿(国民の医療のかかり方、タスク・シフティングの効率化等)、(2)医師の特殊性を含む医療の特性(応召義務の整理)、(3)医師の働き方に関する制度上の論点(時間外労働の上限時間数の設定、宿日直や自己研鑽の取り扱い等)の3つを軸とすることを提議。この日は事務局が示すデータを基に、宿日直と自己研鑽についての議論が開始された。
まず、勤務医の週勤務時間について分析した結果(病院・大学病院勤務医約20万人対象)、週50時間以上が6割以上を占めていた(オンコール待機は除外したデータ)、これまでのデータを紹介。性別、年代、診療科や地域ブロック別に分析されたデータも示され、「属性別に特段大きな特徴は見られない」とされたが、これに対し委員からは「全国的に一律の基準にしてしまったら医療は崩壊する。地域ごと・診療体制ごとにもっと丁寧な分析が必要」という声が上った。
宿日直の類型化は必要? そして実現は可能なのか
さらに四病院団体協議会が今年7~8月に実施した平日時間外の勤務実態についてのアンケート調査からは、当直勤務中(17時から翌9時までの16時間)の診療時間数について、2時間以下だった医師が全体の34%を占めた一方で、8時間を超える医師も19%存在することが明らかとなった。事務局側は、当直勤務の実態としては3つ(ほぼ診療なし/一定の頻度で診療が発生/日中と同程度に診療が発生)に大別できるのではないかとの視点を提供。委員からは、「当直勤務の負担レベルを労基署が判断するようなことは難しく、混乱を招きかねない。診療実態に即した形で、医療者側からみた類型化が必要なのではないか(今村 聡氏、日本医師会女性医師支援センター長)」、「総時間もあるが、断続的に対応している場合、睡眠が確保できない。睡眠の質の確保という観点も加えるべきではないか(黒澤 一氏、東北大学環境・安全推進センター教授)」、「健康への影響が大きい当直明けの連続勤務についての視点が抜けている(村上 陽子氏、日本労働組合総連合会総合労働局長)」などの意見が上った。自己研鑽にあたるもの、あたらないものとは
自己研鑽については、「病院勤務医の勤務実態調査(2017年12月~2018年2月実施)」において「自己研修」として記録された行為を参考に、事務局から自己研鑽と考えられているものの例が提示された(診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬についての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り、自主参加の学会や外部の勉強会への参加・発表準備等、自主的な院内勉強会への参加・発表準備等、自主的な論文執筆・投稿、大学院の受験勉強、専門医の取得・更新[勤務先の雇用条件となっていない場合]、参加が必須ではない上司・先輩が術者である手術や処置等の見学、診療経験や見学の機会を確保するための当直シフト外での待機、臨床研究)。委員からは、「健康管理をしたうえで、必要な自己研鑽が時間内にできるような勤務スケジュールのデザイン、システムの整備が必要(三島 千明氏、青葉アーバンクリニック総合診療医)」、「1つひとつの自己研鑽を評価するのではなく、“自己研鑽手当”のような形で包括的に評価していくことができないか(黒沢氏)」、「“使用者の指揮命令下かどうか”が1つの判断基準とすると、労働者は労働だと思っているが、使用者は自己研鑽だと思っているものが問題になるのではないか(赤星 昂己氏、東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター医師)」などの多様な意見が出された。
今後は、国民の医療のかかり方について9月中にも懇談会が新たに設置される予定のほか、応召義務の解釈についても別途研究班が発足して議論が始まっており、これらの議論を検討会で吸い上げつつ、上限時間数の設定等について複数の試案を提案することも視野に入れ、引き続き議論を進める方針だ。
■参考
厚生労働省「第9回医師の働き方改革に関する検討会」資料
■関連記事
厚労省・医師の働き方改革検討会が初会合-残業規制の在り方など19年3月ごろ取りまとめ
(ケアネット 遊佐 なつみ)
[ 最新ニュース ]
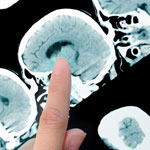
局所進行頭頸部扁平上皮がんの維持療法、アテゾリズマブvs.プラセボ/JAMA(2025/03/31)

CEA中の超音波血栓溶解法、第III相試験の結果/BMJ(2025/03/31)

ベンゾジアゼピンによる治療はアルツハイマー病の重大なリスク因子なのか(2025/03/31)
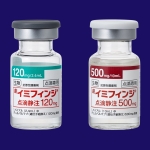
限局型小細胞肺がん、CRT後のデュルバルマブ承認/AZ(2025/03/31)

ベネトクラクス、再発・難治マントル細胞リンパ腫に追加承認/アッヴィ(2025/03/31)

「H. pylori感染の診断と治療のガイドライン」改訂のポイント/日本胃癌学会(2025/03/31)

極端な暑さは高齢者の生物学的な老化を早める(2025/03/31)

一人暮らしの認知症者は疎外されやすい?(2025/03/31)
[ あわせて読みたい ]
今考える肺がん治療(2022/08/24)
あなたにとって、開業の「成功」「失敗」とは?【ひつじ・ヤギ先生と学ぶ 医業承継キソの基礎 】第42回(2022/08/09)
「後継者採用」という甘い誘いに乗ったら…【ひつじ・ヤギ先生と学ぶ 医業承継キソの基礎 】第41回(2022/07/08)
「診療所、知人に売るから大丈夫」、それ本当に大丈夫??【ひつじ・ヤギ先生と学ぶ 医業承継キソの基礎 】第40回(2022/06/06)
Dr.金井のCTクイズ 初級編(2022/05/17)
診療所の売れ行きに直結する「概要書」の大切さ【ひつじ・ヤギ先生と学ぶ 医業承継キソの基礎 】第39回(2022/05/09)
医療マンガ大賞2021「たった一時間されど一時間」受賞者描き下ろし作品(ささき かずよ氏)(2022/04/18)
「急ぎ」のお宝承継をゲットできる医師は…?【ひつじ・ヤギ先生と学ぶ 医業承継キソの基礎 】第38回(2022/04/11)
Dr.田中和豊の血液検査指南 電解質編(2022/04/10)
医療マンガ大賞2021「命のバトン」受賞者描き下ろし作品(ささき かずよ氏)(2022/03/17)

